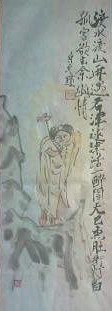
対馬、一支両国共に食糧が不足するので末廬国や伊都国に船で渡り、海産物(対馬国)や竹細工、木工製品などの産物(一支国)を穀物等に換えて食糧を得た。対馬と一支の間の海{対馬海峡東水道}は特に、「瀚海」と呼ばれた。広大な沙漠の如き恐ろしい海と云う意味で在る。大海原、日本海を指したと解釈できる。海を知らない内国人の魏の使節にとっても、彼等を運ぶ船を操る海部人達にとっても危険、此の上も無い船旅で在った。
第二章に、帯方郡に向かう船旅の描写に「持衰」という人が撰ばれて船を守る光景が述べられるが、「持衰」とは、海神に捧げられた生け贄で在った。生け贄を立てて渡らねば為らない恐ろしい海であった。手漕ぎの船や帆を張っただけの小さな船で、海部人等も畏れる海流が激しい海を渡るのである。潮流に流されて其れこそ、「瀚海」に放り出されないとも限らない。
*、「此処で始めて海を渡る事千余里{約七十八公里}、対馬国に至る。対馬の官は卑狗{彦}、副司は卑奴母離{夷守}で、其の国は絶海の孤島に居在する。面積は方四百余里{約三百十平方公里、実際は七百平方公里}で其の地は山が険しく海に迫り、森は深く、道路は獣路の様に細い。戸数は千余りで良田は無く、海産物を食って自活し或いは、南北に船を操って市に出掛け、物々交換をして食糧を得る。
又、南に海を一つ渡る事千余里、此の海の名は瀚海と云って一大国{壱岐国、「大」は「支」の誤字?一支に至る。此の国の官も卑狗、副司は卑奴母離と称する。面積は方三百余里{約二百三十平方公里、実際は百三十四平方公里}で竹や木々の生える叢林が多い。三千前後の居家が在る。田地は段々畑で耕作はしているが、食糧は不足する。対馬国と同様、南北に行って市糴{市で物々交換}して食糧を得る。」
**、筆者按:此の対馬壱岐間の航路を表現するのに、沙漠の様な恐ろしい大海原を言い表す「瀚海」という文字をわざわざ、使用している事は対馬海峡ルート以外の大海原、玄界灘を行く航路のあった事、後に記す「韓国南岸から玄界灘を漕ぎ渡って沖の島に至り、大島を経て宗像に至る」ルートの存在を述べた事が想像される。{第一章第四項、「韓国南岸から倭へ渡る二つのルートー投馬国への道ー」を参照}
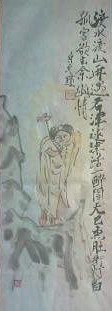
[女王国飄々」
2,大海を渡る
狗邪韓国を発てば朝鮮半島を離れ、倭の本土へ渡る旅が始まる。千余里(約七十八公里)の船旅で対馬島国である。但し、古代には正確な速度計も地図も無く、船頭や漕ぎ手の海部人の感覚に頼らざるを得なかった。実際には、対馬海峡西水道の距離は約五十公里である。対馬島は南北八十二公里、東西十八公里と細長く、面積は約七百平方公里で在る。又、壱岐島は南北十七、東西十五公里である。「魏書倭人条」にはそれぞれ、方四百里{約九百八十平方公里}と方三百里{約五百五十平方公里}と記載される。
千余里で一支島国{壱岐島}更に、千余里で倭国の本土、末廬国{佐賀県松浦半島}に上陸する。実際の対馬海峡{韓国南岸から呼子付近の松浦半島北岸、つまり「魏書倭人条」の狗邪韓国から末廬国の直線距離は二百公里前後で在る。「魏書倭人欄」が述べる距離の約二百三十五公里は、対馬国と一支国の入り組んだ海岸を辿る事を考えると大きな差は無くなる。
対馬島国も一支島国も行政長官は卑狗と呼ばれる。此は「毘古、彦」で後の大和時代には各地方長官・国造を「彦」と称したが、其れに相当するものであろう。副長官は卑那母離と呼ばれる。此の卑那母離は夷守{辺境守備部隊の将軍、軍人}で在る。官に付いてはそれぞれ国によって異なるので其の都度、考察をする。
放屁仙人邪馬台国研究巻二の1
p、1
第一章、邪馬台国への旅 ー扶桑の果て、倭の国々ー
1,帯方郡から倭の玄関・狗邪韓国へ