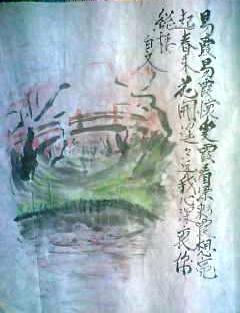
「女王国飄々」
六、倭の人々の暮らしと行事
倭の人々は付き合いが好く、理由を見つけては行き来する。何かを為す時や運を計る時には動物の骨を焼いて占う。其の方法は中国の「令亀の法」{亀の甲羅や動物の骨に占事を書いて火で焼き、出来た裂け目を視て吉凶を占う方法}と同じで在るが、倭人は文字を持た無いので言葉を告げて占う。
集会や座会の時は父や子、男女という席次、序列や区別、規制は無く皆、平等で自由に席に就く。人々は酒を好み、其の機会も多い。 **、筆者按:此は今の日本人の宴会好き、飲酒の機会が多いのと同様??
身分の高い人に見え、ものを告げる等、敬意を表す時は跪き、手を支えてものを申し上げる。
倭人の寿命は皆、百歳、八九十歳と長寿で在ると云う。夫婦生活は、一夫多妻で身分の高い者{原語:大人}は四五人の妻を、庶民{原語:下戸}でも二三人の妻を持つ。妻と為った婦人達には淫らさは無く、互いに嫉妬もせずに仲良く、家庭内は平穏が保たれている。 **、筆者按:此は、長い戦争{第三章、第一項「女王卑弥呼即位」欄を参照}で男女の数に均一性が無くなった事が一夫多妻を生んだ原因かも知れない。
窃盗は無く、訴諍事も少なく、罪を犯した者への罰則は、軽い罪に対しては彼の妻子が捕らえられて奴婢に落とされ、重い罪は門戸{一族}が廃滅され、宗族{親戚}に迄、罰が及ぼされる。つまり、罪は三族に至るとされる。人々の尊卑には互いに序列が在り、秩序が守られている社会で在る。
*、「彼等の風俗は、挙事行来(きょじぎょうらい){事を挙げては互いに行き来}し、運為(うんい){運を測る時}は、骨を輒灼(きしゃく)して卜う。其の占いの辞は令亀の法{亀の甲羅に占う事を告げ}、火?(かたく){火の熱で生ずる裂け目}を視て吉凶を占う。会同{集会}や座起{起ち居振る舞い}には父子や男女の区別は無く、酒を好む。身分の高い人に見える場合の敬意の表現方法は、但だ搏手(はくしゅ)して跪拝(きはい){手を支(つか)えて跪(ひざまづ)いて拝礼する}する。
倭人の寿命を考察すると或いは百歳、或いは八九十歳と長寿である。国の大人{身分の高い者}は皆妻として四五人の婦人を所有し、下戸{庶民}でも二三人の妻を持つ。婦人達は淫さは無く、互いに?忌{嫉妬}をしない。盗窃{盗み}は無く、諍訟{訴え事}も少ない。犯法は、罪の軽い者は彼の妻子を没収して奴婢(ぬひ)とし、重い場合は彼の門戸{一族}を滅して宗族にまで罰を及ぼす。
尊卑には各々差序{序列}が有って互いに臣服するに足りる秩序が守られている。」
**、筆者按:「一夫多妻」と云えばイスラム世界を思うが、「千夜一夜物語」を読む限り、女性は男性に奴隷の如く只、仕えたのでは無い事を知る。「一夫多妻」という言葉から我々、イスラム教を信じない者が、彼らに対して思い描くイメージは間違いで在る事を知る。
女性から積極的に美男を求める事も在ったと物語は語る。若い美男子との恋を成就せんとする或る、美上﨟は彼女の美貌に、己の義務を忘れる判事(カジ)を色仕掛けで味方に付け、彼女に酷い仕打ちをする亭主から法的に、離婚を成立させて侍女や女奴隷を引き連れて恋人の元に走り、彼と生涯を添い遂げる。此の様に女性も結構、生活をエンジョイしていた様である。
また、イスラム世界は厳重な契約社会でも在った。結婚は男女間の契約で在り、其れも判官や立会人を立てなければ為らない神聖な契約が為された。一夫多妻の社会で在るが、他の女性を妻に加える場合は、現在の妻全員の同意が必要で在った。結婚は神{アッラー}に誓う神聖な契約だったのである。
七、倭国の行政
租税の徴収はきちんと為される。国の倉庫{原文:邸閣}も設けられ、徴税の管理が守られている事が記される。
倭国は、各国の間や人々の間では交易が行われる社会でも在った。つまり、各国にはそれぞれ市が立てられ、お互いの有無{余ったものと不足なもの}が交易されたと云う。市では身分の高い大倭と呼ばれる役人が常駐して監督が為され、交易が秩序だっていたと云う。
女王国以北の各国には一大率という特別な監察官が女王国から派遣される。一大率は厳しい監督を行った様で"各国は彼を畏れ憚かった”と記載される。一大率は伊都国に役所を構えて其処で任務に当たった。丁度、中国の各地の状況を調査報告をする刺史の様な役割で在った。
中国の京都{都}や帯方郡、諸韓国へ詣でる倭王の派遣する使いが出発する場合や、帯方郡等から倭へ派遣された使者が到着した場合は、伊都国の津{港}で厳しい検査{原語:蒐露}が為され、文書や中国の朝廷からの下されもの等、女王への贈り物には少しの混乱も生じなかったと云う。
庶民が身分の高い人と道で行き当たった場合は、彼は遠慮をして草叢に隠れ入って道を譲り、言葉を伝える場合や、説明する時は蹲踞して頭を地に額ずけ、跪いて手を付いて平伏して恭敬を示す態度をとる。身分の高い者が応じたり、判ったと言う場合の「おー」という返事は中国の「好(ハオ)」{"好し分かった”}という言葉に中ると云う。
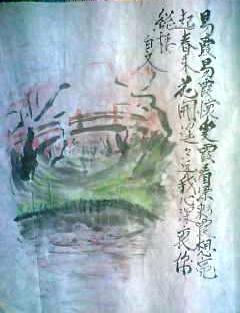
放屁仙人邪馬台国研究巻三の3
第二章、「倭国の人々」ー古の日本人の暮らしp、3ー